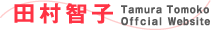コラム
【13.07.06】テレビドラマWomanと生活保護法
福祉事務所の改革がもたらすもの
参議院選挙の前日、10代の若者と政治家の討論企画に参加。息子と同年代の高校3年生が企画の中心を担った聞いて、驚くやら感心するやら。
若者の可能性と力を押し込めるのではなく、正当に評価する、大人の側が発想の転換をしなければと実感。
この企画が終わって帰宅したら、夜10時過ぎ。晩ご飯を食べながら夕刊を手にとって、あ、見たい番組があったと思い出しました。日本テレビのWoman。
急いでテレビをつけると、夫の不慮の事故でシングルマザーとなった女性が、深夜、幼い子供をアパートに残して、居酒屋で働いている場面。
帰宅すると、子どもが火がついたように泣いている。近所の女性が「子どもは犬猫じゃないんだから」と母親を叱責する。
翌日、生活保護を受けたいと役所で相談すると、職員は「税金ですから。子どもたちの将来の予算をもらって生活するんですよ」等々、説得して申請させない。
この間の国会質問がうかんできて、目がうるうるになってしまいました。
生活保護へのバッシングが激しい時に、こういうテレビドラマが放映されるとは。
嬉しいというのとは違います。かき立てられるような気持ち、身体中の血液がドクドクと勢いよく流れ出すような感覚がこみあげました。
このドラマでは、窓口の若い職員は、シングルマザーに寄り添いたいという表情。上司が、これが行政の役割とでもいいたそうに、「水際作戦」を展開するという構造。
福祉の専門家として職員が役割を発揮したら、彼女はどれほど勇気づけられるだろうかと、考えずにはいられない場面でもあります。
夜、彼女がどんな思いで働いているか、子どもたちはどんな状況にあるか、家庭を訪ねればすぐにわかるのに。
生活保護の法案、参議院厚生労働委員会の参考人質疑(6月21日参議院厚生労働委員会)では、北海道釧路市の福祉事務所生活主幹・佐藤茂さんのお話に良い意味で衝撃を受けました。
リーマンショック後の深刻な不況の中で取り組んだ母子世帯への自立支援。
そのなかで、「ケースワーカーは、一人一人と見つめ合う、話を聞く、同じ目線に立つということが最低限必要」と、福祉事務所の役割を認識し直した。
ケースワーカー1人が150人も担当していては、話をきくこともできない、担当する保護受給者を80人とし、さらに60人をめざしている。
高校生が就職希望ならば、生活扶助費で運転免許の取得を認め、これが安定就労に着実につながっている。
就労支援とは、自尊心の回復、就労意欲を育てること。
生活保護への偏見を払拭するため、民間事業所にも足を運んで、就労先(試用もふくめ)の開拓にも取り組む。
一人一人の「自立支援プログラム」については、ケースワーカー以外の支援員が関わって、当事者が意見を言いやすいようにしている。
就労につながり、保護廃止になる時に、笑顔でありがとうございましたと言って福祉事務所を出て行く、それが私たちのやりがいにつながっている。
福祉事務所の窓口には生活保護申請書を常時置いていて、誰でも手にすることができる。
生活保護申請の同行支援にもとりくんでいる、NPO法人ほっとぷらす・藤田孝典さんが、全国の福祉事務所がこうであって欲しい、と話されたことも印象的でした。
「水際作戦」の原因の一つは、福祉事務所の圧倒的な人員不足だと、私も考えています。
一人一人の生活実態、抱えている困難を、同じ目線でとらえるのには、時間もかかります。
事情が複雑であれば、何度かの面談で次第に状況がわかるということもあるでしょう。
また、ケースワーカーが裏切られた感じるよう小さな事件も起こるでしょう。
真面目にとりくめば、精神的には他人の人生を背負うような負担を感じることもあるでしょう。
複数のチームで信頼関係を築きながらの支援のなれば、燃え尽き症候群を防ぐこともできるでしょう。
必要なのは、生活保護法の「改正」ではなく、福祉事務所の改革ではないのか。
専門職として、知識と意欲と経験を育てながら働く職員ではないのか。
参考人質疑で、胸のざわめきがおさまりませんでした。
(この会議録は、7月20日までは参議院のホームページの会議録コーナーから読むことができます。国会図書館の会議録検索にはまだデータが入っていないようです。)