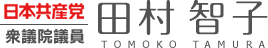(写真)田村智子議員 |
日本共産党の田村智子議員は23日の参院内閣委員会で、生活保護の教育扶助見直しは子どもの貧困対策に逆行すると批判しました。
10月からの生活保護の見直しでは、生活扶助費の最大5%削減に加え、学習支援費も見直されます。現在、家庭内学習とクラブ活動費として定額が支払われていますが、見直しで学校部活動の実費分だけの支給となります。小学生では現在、月額2650円が支給されていますが、年間上限1万5700円(月平均約1300円余)へと大幅に削減され、小学生1人を持つ世帯の場合、年間約3万円の給付減となります。
田村氏の指摘に、大沼みずほ厚生労働政務官も、小学生を持つ世帯では減額になると認めました。
田村氏は、学習支援費は絵本や参考書など幅広い学校外教育費を対象としてきたと指摘。中学3年で部活動を引退し、受験に向け参考書や問題集がほしいときには、学習支援費見直しで支給が受けられなくなるとして、「これでどうして子どもへの支援強化か」と批判。大沼政務官は、小学校では対象が限定され、中学校では部活引退後に支給されないとの指摘もあり、レクリエーション活動なども含め「対象となる経費について自治体と相談したい」と答弁しました。
3月26日(月)しんぶん赤旗より
【3月23日 内閣委員会議事録】
○田村智子君 日本共産党の田村智子です。
昨年十二月に閣議決定された新しい経済パッケージで人づくり革命の柱となった高等教育の無償化についてまず質問いたします。
私は二年前の決算委員会で、日本は大学等の学費が異常に高く、公的な経済的支援が低い、国際的にも突出した学費負担が重い国であるということを指摘をして、大学授業料の値下げ、給付制奨学金の創設を安倍総理に強く求めました。このときは安倍総理も麻生財務大臣も大変冷たい答弁で、給付制奨学金に後ろ向きだったわけですが、それから余り日を置かずに、この給付制奨学金ということがどんどん選挙の公約にもなり、実現の方向に向かっていったと。これはやはり広範な国民が切実にこれを求めていたということの表れにほかならないと思っています。
ところが、この高等教育無償化の検討の方向を見ると、看板倒れにならないかと言わざるを得ないんです。無償化は、真に必要な者に限定し、住民税非課税世帯が対象だと言われます。文科省の推定で非課税世帯の学生は現在一学年六万人ぐらいじゃないかと、四学年で二十四万人程度。大学生数は学校基本調査によると二百五十八万人なので、推計いたしますと、無償化の対象となるのは一割に届かないということになります。現在、国立大学に対しては、大学院生も含め全学生数の一二%、今年度予算で五・三万人に授業料減免ができるような予算措置が行われています。
国立大学でいえば、そうすると現状とほとんど変わらないんじゃないのか。私立大学では、私学助成による学費免除の支援対象は給与所得八百四十一万円までというのが、今それを対象にしているんです。そうすると、今よりも対象が狭まる可能性も高いんじゃないかと危惧されますが、茂木大臣、いかがですか。
○国務大臣(茂木敏充君) できるだけ温かい答弁に努めさせていただきたいと思っておりますが。
昨年閣議決定をいたしました新しい経済政策パッケージにおきましては、低所得層の進学を支援し、所得の増大を図り、格差の固定化を解消するとの観点から、支援対象は低所得世帯に限定することといたしました。ただし、これまでの授業料の減免措置については、それぞれの学校において対象となる学生が決められていたのに対しまして、今回の措置ではこれを思い切って拡充いたしまして、大学、短期大学、高等専門学校及び専門学校の全ての高等教育機関の学生を対象に交付することといたしました。その金額につきましても、国立大学の場合はその授業料を免除して、私立大学の場合は、国立大学の授業料に加えて私立大学の平均授業料の水準を勘案した一定額を加算した額まで対応を図ることといたしております。
そして、数字のお話ありましたが、これは住民税非課税世帯だけではなくて、住民税非課税世帯に準ずる世帯の子供たちについても、住民税非課税世帯の子供たちに対する支援措置に準じた支援を段階的に行うことといたしております。
これまで予算措置としまして、国立大学三百三十億円が運営費交付金、そして私立大学で百億円私学助成が措置されているところでありますが、今般の措置、これは消費税引上げによります増収分、一・七兆円になりますが、この一部を財源として利用することにしておりまして、これまでの支援策より大幅に拡充させていく予定であります。
○田村智子君 これは大学要件などの問題点も指摘されているんですが、じゃ、一点確認しますけれども、大学で見た場合でも今よりも対象は大幅に広がると、無償化です、無償化の対象は大幅に広がると、これはお約束できるということでよろしいですか。
○国務大臣(茂木敏充君) 現行の授業料の減免措置については、学校種別、設置者別にそれぞれ異なる措置がとられておりまして、それぞれの大学等で対象になっておる学生の範囲が決められておりますが、今回の措置、どんなに貧しい家庭に育っても、意欲さえあれば専門学校、大学にでも進学できるように、真に支援が必要な子供たち全てにつきまして高等教育無償化すると、こういう考え方に立っておりまして、基本的に対象は広がると、このように考えております。
○田村智子君 この真にを本当に強調されるので不安になるんですね。
例えば、東京大学は学生自治会の運動も受けて、世帯年収四百万円以下の学生は授業料免除なんですよ。これ、国の基準に大学が合わせるようなことになれば、むしろ後退してしまうという懸念が出てくるわけです。
ですから、私は文科省の高等教育局にも、呼んで、どうなるんですかということをお聞きしたんだけれども、今その減免制度を担当している文科省の高等教育の方々は、自分たちは無償化検討の、何というんですか、担当ではないとおっしゃるんですね。なので、じゃ、その無償化担当の方、来てくださいといって、改めて説明を聞きまして、それで、今の国立大学がそれぞれどういう基準でもって減額や免除をやっているのかと調べることが必要なんじゃないのか、こういうことをお聞きしましたら、そういう調査はやるつもりないと。なぜなら閣議決定で住民税非課税世帯を対象とすると決めているから、これに沿った制度設計を進めるんだと、こういうことを言われちゃったんですよ。
私、今の学生の実態、真に必要なというのはどういう学生なのか、それから、今大学はどういう免除制度、減額制度を持っているのか、これらをきちんと調査をして、これが充実できるのかどうかということを踏まえて検討を行うべきだと思いますけれども、もう一度、大臣、お願いします。
○国務大臣(茂木敏充君) 今回の高等教育無償化につきましては、これまでの支援策とは、先ほども御説明申し上げたように、別予算でありまして、各大学がこれまでそれぞれ独自に行っている支援策が今回の支援措置の対象外であっても、引き続き実施していただくことに問題はない、このように考えているところであります。
その上で、現行の授業料の減免制度、先ほど申し上げましたように、学校種別、設置者別にそれぞれ異なる措置がとられているところでありますが、今回は意欲さえあれば専門学校、大学にもみんな進学できる、こういう高等教育の無償化、これを共通の考え方としておりまして、思い切ってこの対象も拡大をしていきたい、この方針に基づきまして、もちろん現行制度の実態も踏まえつつ、しっかりと制度設計してまいりたいと考えております。
○田村智子君 今、各大学でやっているのも、運営費交付金がそうやって措置されているからなんですよ。この分がどうなるかということも含めて大問題になってくるので、現行の制度についてはきちんと検証していただきたいということを重ねて要求しておきます。
次に、給付制奨学金の拡充についてお聞きします。
学業に専念するためとして、学生支援機構が行っている学生生活調査のうち、修学費、課外活動費、通学費、食費、居住・光熱費、保健医療費等を念頭にして、給付額の引上げということが検討されていると。ただし、自宅生については食費、居住・光熱費はその額からは除かれるというふうに説明をお伺いしています。
これも試算してみました。そうすると、二〇一四年度調査に基づきますと、国公私立の平均で自宅生年額約三十六万円、自宅外生で約九十七万円。そうすると、今の制度との単純比較で、自宅外生は大幅に引上げになるんですけれども、自宅生についてはほとんど変わらないんじゃないのかなという試算になるんです。
実際にはここから更に減額されることがあるんじゃないかという危惧もあります。例えば、国立大学では、授業料の減免を受けている学生は、この給付金の中から二万円引かれるんですよ。だから、自宅生というのは事実上、受けられないんです、これ二万円引いちゃったらゼロになるから。で、これは同じ運用になるんじゃないのかなと。学費無償を受けたら、その分引かれるんじゃないのかなと、一定額が。
あるいは、自宅生については、生きている限り誰だって食費は必要でしょうという意味で、食費分は見ないよという説明もされているわけですね。そうすると、じゃ、そういう自宅生が負担している食費分というのは、みんなが負担するのが当然だからという理由で、これ、自宅外生の給付額からの控除のベースになるんじゃないのかと、こういうことが危惧されるんですけど、この点、文科省、いかがでしょうか。
○政府参考人(信濃正範君) ただいま二つのことを御指摘いただきました。一つは、授業料免除、ここの部分が減額されるのではないか。それからもう一つは、食費の部分についてどうなるか。
まず最初の、授業料免除の件についてですが、平成二十九年度から先行実施しまして、平成三十年度から本格実施をしております今の給付型奨学金制度、ここでは、おっしゃるとおり、国立の大学等に通う学生が授業料の全額免除を受ける場合には給付月額を減額するという扱いになっております。一方で、昨年十二月に閣議決定しました新しい経済政策パッケージ、ここの中では今度の新しい給付型奨学金についてのコンセプトが書かれておりますが、ここでは授業料の減免措置の拡充と併せ、給付型奨学金の支給額を大幅に増やすということを明記しております。したがいまして、授業料免除に加えて給付型奨学金が支給されることになると、こう考えております。
それから、もう一つ、食費の方でございますけれども、これは、例えば自宅生の住居・光熱費ですとか食費、こういうのは必ずしもその学生個人の支出ではないということ、それから、ほかの学生とか高校を卒業して働いている人などとの公平性の観点、こういったことを考慮しますと、計上しないということで、自宅外生に限って追加的に要する経費として対象とするというふうにしているところでございます。
○田村智子君 控除しないという方向ということなんですね。
○政府参考人(信濃正範君) 今申し上げたのは新しい経済パッケージに書いてあることですが、自宅外生の住居・光熱費ですとか、御指摘がありました食費の実際の計上額をどうするか、ここについては今後検討していきたいというふうに考えております。
○田村智子君 やっぱり食費分まで見なければ大切な生活費の分というのは見られなくなっちゃうわけですから、これ、控除しないでちゃんと出してほしいということを要望しておきます。
問題となるのは生活保護世帯なんですよ。今回の生活保護制度の見直しでも、世帯内就学というのは認められなくて生活保護世帯から事実上分離する、一緒に住んでいても分離するので、その学生分の生活保護費は出ないという扱いになってしまいました。ただし、住宅扶助費の分は減額しないということにとどまった。これでは、学生の生活費、保障されないままになってしまうわけです。
生活保護部会では、本来、教育政策で見るべき課題ではないかという議論があったので、あえて文科省にお聞きします。
先ほど指摘したとおり、自宅でいる場合は、食費などは学生自ら負担すべきものというふうにされて、支援の拡充の対象から外すということも否定をされないわけですよね。保護世帯の子供さんの場合、本当に今でも相当な決意をして大学進学をしています。実際に、大変なアルバイトもこなしながら、それでも食費を切り詰めて生活しているという学生は大勢いるわけです。これ、低所得世帯も同じだというふうに思いますけれども。
これ、学業に専念するためというのならば、生活保護世帯で大学等に進学した場合も含め、また食費もちゃんと勘案した生活費分を公的に保障する、これは検討すべきだと思いますが、いかがですか。
○政府参考人(信濃正範君) 新しい経済政策パッケージ、この中では、高等教育の無償化について、生活保護世帯を含む住民税非課税世帯の意欲ある全ての子供たちに対して給付型奨学金の増額及び授業料減免の拡充を図ると、こうされております。生活保護世帯もしっかり含むとなっております。ただ、あわせまして、給付型奨学金の支援対象経費については、他の学生との公平性の観点も踏まえ、社会通念上常識的なものとするということも記されております。
こういった閣議決定の内容を踏まえまして、具体的な給付の在り方については、学業に専念できるようにするため、学生生活を送るのに必要な生活費を賄えるよう措置するという考え方に基づいて、今後、具体的には検討していきたいと考えております。
○田村智子君 具体的なことがほとんどお答えいただけなかったんですが、冒頭、茂木大臣は、温かくというふうにおっしゃっていただきましたので、私が指摘した懸念が払拭されるよう、是非具体化を進めていただきたいというふうに思います。
次に、生活保護の基準の引下げに関わる問題を質問したいと思います。
これは、生活扶助基準の見直しで最大五%の引下げ、これは子供のいる世帯も例外ではありません。加えて、保護費の中の学習支援費が、今は家庭学習プラスクラブ活動の費用で定額支給なんです。今日、資料もお配りしました。それが、今度はクラブ活動に充てる経費のみとされ、精算払いに見直されることになります。
これまで家庭学習というのは、絵本を含め子供が読む本、参考書、塾などの習い事、模擬試験の受験費など、幅広い学校外教育を対象としていました。これをクラブ活動だけに限定するというのは大変問題で、これは、小学校、中学校、高校、それぞれで年額上限額を示した資料を見比べていただくと分かるんですけれども、小学校でいいますと、今だったら年間で三万一千五百六十なんですね。これが大幅に引下げになってしまう。半分程度になってしまうということですよね。確認します、厚労省。
○大臣政務官(大沼みずほ君) お答えいたします。
今回の生活保護費の見直しにおいては、生活扶助基準本体のほか、子供のいる世帯に対する扶助や加算についても検証を行っているところです。教育に係る費用のうち、御指摘の学習支援費については、支給対象をクラブ活動に係る費用として整理し、支給方法は活動の状況に応じて実費で支給することとしたものであります。
この学習支援費の金額につきましては、文科省で実施されております子供の学習費調査を基に、クラブ活動に係る費用の実態に合わせて設定することといたしました。その結果、実費支給の上限額まで利用する場合、クラブ活動が盛んになる中学生では年間五千円、高校生では年間二万一千円の増額となる一方、クラブ活動に係る支出が少なかった小学生では減額となったものでございます。
なお、委員御指摘のとおり、これまでの家庭内学習に必要な経費は児童養育加算で評価するものとして整理させていただきました。
○田村智子君 児童養育加算もほとんど、減額になるのはごく一部なんです、あっ、増額になるのは。小学校の三人の世帯だったらこれ減額になっちゃうというものですからね。
それで、小学校ってほとんどクラブ活動に参加している子いないんじゃないですか。低学年でクラブ活動ってないと思いますよ。そうすると、丸々ゼロになっちゃうんですよ。中学も、中三、高三の夏で運動部活動は大体引退ですよ。そこから塾に行きたいとか参考書買って受験勉強しようというときに、そうしたらなくなっちゃうわけですよ。そういう扱いでいいのか、これが生活保護世帯への子育ての支援強化と言えるのかということだと思います。
それで、これちょっと、もう時間がないので松山大臣に併せてお聞きしたいんですけど、今日、資料の二枚目、三枚目は、子供の貧困対策センターあすのばが、二月十三日、議員会館で子供の生活と声、一千五百人アンケートの中間報告の集会を行ったときのものなんです。このアンケートの対象は、あすのば入学・新生活応援給付金を受けた生活保護世帯、住民税非課税世帯の子供と保護者。回答は、子供一千四百二十五人、保護者一千七百七十人。
強調されたのは、子供たちの諦め体験。七割近い保護者が、子供が塾や習い事を諦めたことがある。海水浴やキャンプなどの体験も二五%。また生活保護世帯の子供が、より諦め体験が多いと。部活動でいうと、生保世帯二〇%、生保なし一四%、海水浴、キャンプなどの体験は、生保世帯三〇%、生保なし二五%と。
子供の貧困問題に取り組む有識者の方々からも、休日の旅行とか映画、演劇鑑賞とか、様々な体験活動の欠落は学習意欲や自己肯定感に影響を与えると、これ以前から指摘されているんですよ。そうすると、子供たちの実態からも、豊かな学習体験活動を保障するような、むしろ広い意味での家庭教育の支援、これは充実させることこそ必要だと思いますが、松山大臣の所見を伺います。
○国務大臣(松山政司君) 田村委員にお答えいたします。
子供たちの誰もが夢に向かって頑張ることができる社会をつくることは内閣の基本方針でございます。
貧困の状況にある子供たちは、経済的な困難にとどまらず、生活や学習面での習慣が身に付かない、あるいはコミュニケーション不足、心理的なストレス、様々な困難を抱えておりまして、それらが諦めの経験につながってしまう面もあると考えています。そうした子供たちにとって、家庭教育の充実も含めて、学習に取り組むための環境の整備や学習意欲につながる様々な体験が非常に重要であると考えています。
先日、ICTを活用した、低料金で子供たちの学習支援を行っているNPO法人、視察をしてまいりましたが、子供たちがこうした学習支援を通じて主体的に学習に取り組めるようになり、また将来へ期待を膨らませる姿を見させていただいて、大変感銘を受けたわけでございますが、政府におきましても、子供の貧困対策に対する大綱、これに基づいて、厚労省における生活困窮世帯の子供への学習支援、また文科省における地域住民の協力による学習支援などと施策を進めておりますが、内閣府としても、関係省庁と連携を取りながら注視をし、しっかり取り組んでまいりたいと思います。
○委員長(榛葉賀津也君) 前段の質問について、厚生労働省。
○大臣政務官(大沼みずほ君) 今回の検証におきましては、子供がいる世帯に対する加算や教育に関する給付につきまして検証を行っておりまして、子供がいる世帯の約六割で生活扶助費の基準額の増加を見込んでいるところでございます。
確かに、委員御指摘のように、小学校では対象者が限定される、また中学校ではクラブ活動引退後に支給されないなどの御指摘があることから、今後、様々なそういったレクリエーション活動というものが考えられることでありますから、地方自治体と協議しながらその対象となる範囲の詳細を検討してまいりたいと思います。
○田村智子君 一言だけです。
前任の子供の貧困対策大臣は加藤厚労大臣なんですよ。この学習支援費をこんなふうに見直すことはやっぱりやめてほしい。これ、松山大臣と加藤大臣、是非御協議いただきたいということを申し上げて、質問を終わります。