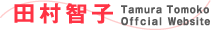HOME - 論文・レポート - 高学費に拍車をかける財政構造改革法
高学費に拍車をかける財政構造改革法
第141臨時国会では、「財政構造改革法」(以下「財構法」)が成立した。これは、国の財政赤字を理由に、来年度から3年間にわたり、国民生活にかかわる予算をあらゆる分野から抑制することを目的としている。
その一方で、浪費のおおもとである公共事業や軍事費は、相変わらず「聖域」とされ、しかも3年間の集中期間が過ぎても赤字体質から抜け出すことは不可能という、無責任きわまりない内容である。わが党議員団は一丸となって、この法案が何をもたらすのかを多面的に告発し、廃案をめざして奮闘した。
「財構法」による歳出抑制の対象には、国立学校の予算および私立学校への補助金が含まれている。これらは、大学の学費に大きな影響を与えることとなるだろう。財政構造改革が国民に何をもたらすのか、学費の問題から明らかにしたい。
自己破産まで発生---高学費負担の現実
「財構法案」の審議がすすむ11月13日、全国から600人近い学生が国会周辺に集まり、学費値上げ政策反対を訴えた。学生たちは、高学費に苦しむ学生と親たちの実態を怒りをこめて告発した。
「父は単身赴任、母はいつも大変だなといいながらも仕事をがんばっています。そんな家族をみるのはつらいです」、「お金のない学生は学問をするという権利も奪われてしまうのですか。バイトで生活費を稼ぐため勉強が十分にできません」、「生活費5万円をだすので精一杯です。食費を切りつめてどうにかやっていたところ、貧血を起こしてしまい、さらに苦しい状態になってしまいました」、「サラリーマンの父が土日に土方のバイトをしている」(学生たちへのアンケートによる『学費黒書』)。
■私大生の家庭は借金づけ
とりわけ学生の7割以上をしめる私大の学費負担は、もはや限界をこえるものとなっている。私大の初年度納付金は、平均で120万円以上、学部別でもすべてが100万円をこえている。自宅外通学となると、家庭の負担は可処分所得の42.5%をしめるという驚くべき統計もでている(『国民生活白書』96年度版)。子ども二人が私大に入学したら、家計は完全にパンク状態になるということである。
実際に、親の収入の学生やアルバイトでは負担しきれず、入学と下宿の準備のために借金をする家庭は26%、医歯系の学部では6割の家庭が200万円をこえる借金をしているという(東京私大教連『私立大学新入生の家計負担調査』96年度)。日本弁護士連合会の資料によれば、最近では教育費を原因とする自己破産のケースまで生じており、その事例は、ギャンブル破産の約2倍にのぼっている。
■うなぎのぼりの国立大の学費
国立大学はどうだろうか。来年度の国立大の初年度納付金は74万4200円、これは81年の私大平均とほぼ同額である。このうち授業料は46万9200円、1970年の1万2000円から実に40倍近い値上げである。入学金は27万5000円、70年の4000円の約70倍である。(表1参照)
文部省は授業料、入学金をどのように位置づけているのかを聞いたところ、授業料とは「授業というサービスにたいして、必要経費の山部の応分負担を求めるもの」だという。入学金は「施設を使用する身分を有するために支払うもの」、いわば施設使用の権利金といえるだろう。しかし前述の異常な値上げは、この説明さえも成り立たないものとしている。
政府・文部省は一貫して、「社会経済情勢、私立大の授業料の水準などを総合的に勘案して」国立大学費を決めてきたと説明をしている。しかし、参議院の特別委員会(11月17日)で、日本共産党の阿部幸代議員の質問にこたえ、経済企画庁が「(国立大学費は)公共料金の中では上昇率が最も高くなっている70年から96年では、電気代の値上げ約1.6倍、都市ガス約2.7倍)」と答弁しているように、結局は、私立大なみに値上げすることだけが目的とされてきたのである。驚いたことに、町村文部大臣はこうした政策を是認し、「(私立大と)あまり差がありすぎるのはいかがかということもあり・・・今約1.6倍ぐらい私立大学の授業料が高いという比率」になったと答弁しているのである。歴代自民党政治による学費値上げ政策は、ついに低所得者層を高等教育から締め出しはじめる段階まできている。
■低所得者を大学からしめだす
文部省の『学生生活調査96年度版によると、世帯を収入順に5つの段階に分けたうちの最低収入層(五分位第一階層。年収約550万円以下)では、前回調査の94年度から96年度の2年間に大学進学率が10%も落ち込み、関係者の間にショックを与えた。平均進学率が上昇しているもとで、この層だけが激減しているのである。その理由とするところが、経済的問題以外になにがあるというのだろう。(表2参照)
大学進学をはたした後も、高学費は学生たちから学ぶ権利を奪っている。
東京のある私立大では、一年間に40〜50人が授業料未納で退学を余儀なくされているという。「父は一日12時間以上も働いている。私が大学をやめればこんな無理をさせなくてもすむのにと考えてしまう」、私立大の学生の切実な声である。また、「妹の進学の幅を狭め結局就職希望」「弟は希望の大学をあきらめ地元の国立大を受験せざるをえない」など、弟妹の進路にまで影響がおよんでいる。
教育基本法第三条は、「すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであって、人権、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によつて、教育上差別されない」と、教育の機会均等の原則を明記している。
教育のもっとも基本的なあり方を示す法律を、政府みずから掘り崩すことが、どうして許されるだろうか。
「財構法案」審議でなにが明らかになったか
今日の学費負担は、前述のようにすでに多くの国民にとって限界をこえるものとなっている。いま求められるのは、学費値下げ政策であるにもかかわらず、橋本内閣の選択は「財構法案」によるさらなる高学費化である。
■学費値上げへの引き金
「財構法」第17条には、集中改革期間(98年度から3年間)には、国立学校特別会計への一般会計からの繰入金の額、および私立学校の経常経費にあてる国の補助金の総額が、いずれも前年度を上回らないようにすると、明文の規定を設けている。
私立大の経常経費は、この10年間で一兆円もの伸びをみせている。国庫助成は、この間、国民の運動によって不十分とはいえ増額してきたが、経費の上昇にはまったく追いつかず、結局学費の値上げが続けられた。こういう状況のもとで突然、「来年度から国庫助成は増額なし」となればどうなるか。経費の伸びのほとんどを学費値上げで補わざるをえない。
しかも、「財構法案」が提出される前から、私立大からは、今後の経営について次のような予想がだされていた。「(長引く不況の影響で)ごく近い将来に、手数料・寄付金・資産運用収入などが増加に転じる見込みはほとんどない」「ますます学費納付金に依存する体質が強化される危険性もある」(『全国私立大学白書 96年度版』国庫助成に関する全国私立大学教授会連合)。
国立大ではどうだろうか。国立大の経費も私大の経費と同様に伸びており、来年度文部省概算要求では1.15%増が見込まれている(国立大の経費がほとんどをしめる「国立学校特別会計」)。
これにたいし、一般会計からの繰り入れが縮減されれば、不足額は大学の自己収入(学費納付金のほかに国立大学付属病院の収入など)で補うしかない。病院収入を伸ばして半分を補ったとしても、残り半分は学費値上げに依存せざるをえない。
では、どれだけ学費負担増が見込まれるのか。10月22日に衆議院の特別委員会で、日本共産党の石井郁子議員が試算を明らかにした。それによれば、99年度の私大の学費(平均)は11万円以上の値上げで130万円を突破、国立大では42万円以上もの値上げになり100万円をこえることになる。
■明言を避ける政府答弁
このような事実にそくした指摘にたいし、橋本首相も町村文相も、学費がどうなるのかを最後まで明言しなかった。それどころか首相は、「教育費の負担を少しでも軽減する」ということさえ口にした。
医療費や年金については正面から国民に負担増を求めるのにたいし、学費については当然見えてくる負担増を覆い隠そうとしたのだ。これは、学費の父母負担が限界にたっしていることを、政府みずから認めざるをえないことの現れである。
では、学費値上げに依存せずに、予算削減をどうのりきるというのだろう。町村文相は「経営努力」「教職員の定員削減」などで経費削減を求めていきたいという。しかし、大教室での講義、施設の老朽化・狭隘化など、今日の劣悪な勉学研究条件をみれば、文相のいう「経営努力」もまた限界であることは明白である。
結局は、「現下の財政事情により、予算削減は仕方がない」ということだけが、彼らの明確な答弁であり、それは「負担軽減」という言葉とは裏腹に、学費値上げへの道に結びつかざるをえない。
■「学部別授業料」導入をはかる大蔵省
総理や文相が高学費化を懸命に否定する答弁を続けている最中、時事通信社「官庁速報」(11月5日)は、「大蔵省は、国立大学の授業料を引き上げる方針を固め、近く文部省と調整に入る」と報じた。「財政構造改革の一環として、授業料引き上げによって大学の自己収入を増やし、国立学校特別会計に投入している一般会計からの繰り入れを減らすのが狙い」だという。わが党議員団の指摘が、単なる推測ではなかったことを証明する内容である。
さらに重大なことに、「全学部一律の現行制度を改め、学生一人当たりにかかるコストの違いを反映させ、理工系の授業料を人文系より高く設定する『学部別授業料』の導入を検討する」としている。その理由は、「国立大の学生の保護者の年収が、私立大と比べそん色ないこともあり、授業料を引き上げても支障はない」「私立大では文化系と医歯系とで四倍以上の授業料格差があり、受益者負担の観点に照らし合わせると、国立大でも学部別授業料の導入は妥当と判断した」からだという。(表3参照)
私大の医歯系の学部では、初年度納入金は470万円にものぼる。こうした格差が国立大にまで持ち込まれれば、低所得者層は完全に門戸を閉ざされてしまうだろう。衆院・文教委員会(11月19日)で石井議員がこの報道についてとりあげたさい、文相はこれまでの文部省見解を踏襲し、「学部別授業料はやるべきでない」と答弁した。しかし、「財構法」が成立した今日、大蔵省の姿勢はこれまでとは質的に異なり高圧的になるであろう。このような政策を阻止するためには、急速な世論と運動の高まりが要請される。
■奨学金制度で負担軽減ができるのか
「財構法案」の審議で、文相はたびたび、奨学金の充実で負担の軽減をはかりたいと答弁をした。そこで、奨学金制度の問題についても若干のべておきたい。
国が関与する育英会奨学金は、高校の成績、経済状況などをみて、大学が選抜した学生に貸与される。奨学生の人員は決まっており、毎年の枠の拡大は微々たるものである。現在、奨学生は四年制大学の学生数の1割にすぎない。
しかも、欧米諸国ではほとんどが賞与(返済の必要なし)であるのにたいし、日本ではすべてが貸与、3人に1人は年利2〜3%の利子をつけて返済しなければならない(第二種)。これは奨学金というよりも、国家による教育ローンである。
高校から奨学生となり、自宅外通学で大学に入学し博士課程まで第二種の奨学金貸与を受けた場合、貸与総額は975万円にものぼる(利子がつくので返済総額は更に多額になる)。不況で就職も不安定なときに、学生に1,000万円もの借金を負わせて社会に送り出す、これが日本の奨学金制度の実態である。
それでも、毎年貸与人員枠をはるかに上回る申請がだされている。奨学金なしには生活が成り立たない学生が、それだけ多数にのぼっているのである。
学費値上げを阻止するために
高等教育をうけるために高額の負担を当然とするような国は、欧米諸国では例がない。文部省の資料『教育指標の国際比較』(1996年版)をみると、入学金というものは欧米諸国にはそもそも存在しない(ごくわずかの登録料徴収はある)。授業料も、イギリス、ドイツ、フランスでは公的に保障するのが当然とされ、基本的に無料(注)である。アメリカでも州立四年制大学では、実習費などを含めても日本の国立大の6割程度である。
(注)「イギリスでは、財政事情から授業料徴収が検討されているが、年収の低い方から3割の学生は免除(授業料・生活費とも)、その他も年収に応じて上限(年額約20万円)を決めた徴収を検討。ドイツでは、在学年数が通常期間(9学期・4年半)を2年(4学期)以上上回る学生について、一学期約7万円の授業料を課すことを決めた。こうした政府の方針に、イギリス・ドイツとも抗議の声が高まっている。
日本の高学費は、国内の法律に照らしても道理がない。教育基本法はその前文で、「民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする」「この理想の実現は、根本において教育の力に待つべきものである」と高らかに謳っている。このことは、教育の最終的な受益者が社会であり国家であることを示している。そして、前述の通り「教育の機会均等」を明記し、「国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず経済的理由によって就学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない」と、行政の責任を示している。
全国各地で進行する大規模開発、在日米軍への「思いやり」予算、そして相次ぐ金融企業破産への公的資金導入の動きをみても、「国の財政が赤字だから仕方がない」という口実が破綻していることは明らかである。学費値上げ政策に道理のかけらもないことを示し、政府の責任を追及していくことが、ますます重要となっている。加えて筆者は、国立大授業料減免措置の拡充、育英会奨学金の枠の大規模な拡大、第二種奨学金(利子あり)の無利子化(少なくとも公定歩合以下とすること)などの緊急政策が必要であることを付記したい。