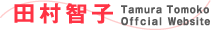コラム
コラム
『七いろのはなびら』
ソビエトの童話のやさしさが見えてきます
西郷竹彦 訳 太田大八 絵
偕成者(1968年7月発行 当時の定価350円)
魔法の力を期間限定(回数限定)でさずかって、望みをかなえることができる
――童話の一つの定番ですね。
そういうお話のなかでも、子どもの頃、私が大好きだったのがこの絵本。
女の子ジーニャが、ドーナッツを買って帰る、この最初の場面にまず心ひかれました。
ドーナッツは箱にも袋にも入っていません。
なんと、穴にひもを通してぶらさげて歩くのです。
外国の生活を垣間見たような、不思議な気持ちをもちつつ、
それでも違和感なく受け入れることができる――すぐれた児童文学のなせるわざです。
お母さんに頼まれた買い物、ところが後ろ手に持っているうちに、ドーナッツは犬に全部食べられてしまいます。
泣いている女の子の前に現れたのは、不思議なおばあさん。
あらためて読んでみて気がつきました。
困っている人を助けた見返りに魔法の力を手にする、というパターンが多い中で、
この絵本は、困っている女の子をただ助けるために、魔法の花が手渡されていました。
なんだかいいですね。
七枚の花びらが一枚ごとに色が違う、その花の美しさが子どもの頃の私には、なんだかいとおしかった。
花びらを一枚ちぎって呪文をとなえる、願い事をかなえたい気持ちと、花びらをとっておきたい気持ちにゆれながら読み進めた記憶があります。
ジーニャの願い事は、お母さんに叱られないために,、自分の失敗をおぎなうものだったり、
男の子とたちの「北極探検ごっこ」に対抗しようと、本当に北極に行ってしまったり(寒さに凍えてすぐ帰ってくるのです)。
もったいない!と読者をやきもきさせる、「願い事」童話ならではの進み方ですよね。
満足できる「願い事」がないままに、花びらは最後の一枚に…。
ここで登場するのは、障害をもって生まれた男の子。
「思い切り走ったことはない」という男の子の言葉に…。
子ども心にも、障害者が童話に登場することに驚きました。
ジーニャが「私がなおしてあげる」という言葉もそぶりもないまま、ひそかに呪文をとなえる、これも胸に響きました。
男の子が駆け出す、ジーニャも後をおって走り出す。
その挿絵のジーニャの表情は、やさしさに満ちているようでした。
ソビエトの児童作家の作品だと理解したのは、大人になって読み返してから。
民主主義の抑圧や他の民族への抑圧など、ソ連は社会主義とはいえない道を歩んだ国です。
けれど、その初心、とりわけ民衆のなかにあった志・理想はどうだったのか。
この絵本、娘が入学前に病院に入院したとき、持って行って読み聞かせた本です。
呪文がおもしろくて、隣のベッドにいた子も一緒に聞いてくれました。
そしてしばし、「どんな願い事する?」と考えましたっけ。
魔法では病気や障害に向かうことはできないけれど、
そのつらさや、痛みに思いをはせて、当たり前に手を差し伸べあう、そういう世の中にしたいですね。